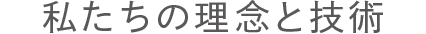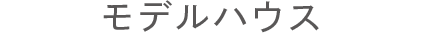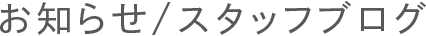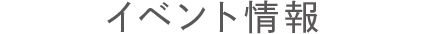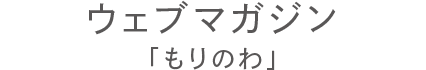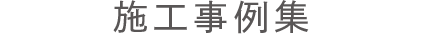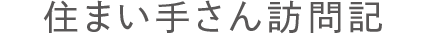第3回 試行錯誤の学びの日々
自然と共にある設計思想の話|山田貴宏さんインタビュー

坂元植林の家「まちのえ」「さとのえ」の設計をお願いした、ビオフォルム環境デザイン室の山田貴宏さんは、設計はもとより、ご自身の住まいや暮らしぶりにおいても、「自然や環境と調和して、自然の恵みを分かち合う暮らしをつくる」というビジョンを具現化されています。第1章の第1回と第2回では、その住まいと暮らしについて語っていただきました。第2章では、環境建築を志すまでの歩みや、建築の役割や望ましいまちづくりについて語っていただきます。(もりのわ編集部)
第2章 右肩あがりの時代から循環のデザインへ
第3回 試行錯誤の学びの日々

.
大学での専攻に「建築」を選び、就職するまで
元々、高校生の頃までは、エンジニアリングの分野に興味がありました。父親が飛行機のエンジニアだったことが大きな要因で、飛行機もかっこいいし面白いなと思っていて・・・。ただ、大学進学にあたって、仕事に繋がるような専門分野を学びたいと思って、何を学ぶべきか、何を学びたいかと考えた時に、建築の道に進むことにしたんです。
父親の仕事の関係で、小学生の頃、イタリアに住んでいました。幼稚園の年長の頃に行って、小学4年生で帰国しました。その頃の、街の景観や、そこから感じられる歴史や文化が、とても良い記憶として残っていて、その影響が強かったんでしょうね。大学受験を意識し始めた頃、一生できる仕事は何だろうと考えたときに、建築とか都市計画とか、そういう分野に進みたいと思い始めたわけです。
感受性も強くなっていた時期に、イタリアの重層的な歴史のある街の中で過ごしていたので、日本に帰ってきたときに、子ども心にびっくりしたわけです。ヨーロッパは国が地続きなので、親に連れられていろんな都市にも行きました。ヨーロッパの歴史観とか文化的な景観とか、それを見てきて日本に帰ってきたとき、子ども心に「なんだ、この汚い街は」と、感じてしまったんです。戻ってきたのは千葉だったので、開発もかなり進み、地方に残っているような歴史的な街並みなどもほとんど無くなっていました。
大学を受けるときに、自分の仕事として何をやろうかと一応真面目に考えたわけです。実際、僕らが大学にいるときは、バブルの時期だっただから、学部を問わず、自分が選んだ学問とは関係なく就職はできるということもあって、建築学科を出たけど銀行に就職したり証券会社行ったりとか、そういう学生もたくさんいましたが、自分自身は、一生の仕事として建築をやっていこうと、早稲田大学の建築学科に入ったわけです。
でも当時は、バブル期だったこともあって、いわゆるポストモダンみたいな建築が流行っていました。私の非常に浅はかな理解のもとですが、モダニズムが進みすぎて、もう一回ちゃんとルネサンスじゃないけど、建築をヒューマンなものにしていこうという発想自体はよかったと思います。ですが、結局それがバブルと相まって、金に任せて豪華なものを建てるという、ちょっと筋違いな方向に行っていたと思っています。
そういう時代に建築学科に行ったので、少し幻滅してしまいました。イタリアみたいに、歴史が積み重なった、重層的な建築や都市というものを目指したかったのに・・・。2年に進級したころ、悩んでいた時期があって、建築学科をやめてもしようがないし、どうしようかな、と・・・。そこでまた真面目に考えるわけです。そもそも建築の原点って何だろう?と考えていって、「やっぱりシェルターなのではないか」というところに行きつきました。その人が住んでいる場所の気候風土と対峙して、ときには気候風土の持っている良さを取り入れ、あるときはその気候風土の厳しさに抗うためのシェルターのようなものであるべきだと思ったわけです。そう考え始めて、健全で健康的なシェルターを現代に作るにはどうしたらいいかということで、環境と建築がインターフェースする部分、そのあたりに、これからの大切なテーマがあるのではないかと思うようになっていきました。
環境問題もいろいろどんどん顕在化していった時代ですから、学校の外の環境セミナーなどに参加して、地球規模での深刻さも理解できてきて、それを解決するために建築にできることは何か?ということを考え始めた時期でした。だから、4年生になって研究室を選ぶ時に、環境系の、都市環境をテーマにした研究室にしました。尾島俊雄先生という、のちの建築学会長も努められた方で、発言力もあって、なにより発想がとてもユニーク。その先生のもとで、都市をまるっと環境的に考えるということを志向しました。

.
だけど、次の挫折がまたくるわけです。いざ就職という時期になって、僕ら建築学科といったら、一般的には、工務店だ、ゼネコンだ、あるいは設計事務所だということになるわけです。だから、都市をマネジメントするとか、都市を環境的にどうこうするとかということができる職場は、当時、僕としても考えが浮かばなかった。やはりまずは設計という仕事をボトムアップでやっていく必要性も感じて、一応ゼネコンを就職先に選んで、清水建設に入りました。会社には、地球環境室という部署もあったけれど、何をやっていたかというと、建築現場の廃材、ゴミ、それをどうするかという問題を扱っていました。それはそれで大事なことだけど、地球環境とは言っても、当時はそれくらいの認識でした。
僕が配属になったのは、入社した時は地域冷暖房エンジニアリング部という名称で、省エネがテーマの部署です。エネルギーの効率化ということで、都市の中で集中的に冷暖房の熱源プラントを作って、そこから冷水、温水を地下配管で配るというシステムが、ヨーロッパやアメリカでは一般的になっていた時期で、僕の大学のときの研究テーマも、そういう集中的な冷暖房の仕組みを入れたらどれだけ省エネになるかということを都市レベルで考えることでした。そういうことも考慮されて、地域冷暖房のプラントの設計が中心の仕事でした。
省エネという大局的な目標のためには、プラントのような仕組みの設計というのは、重要なことだとは思いますが、建築と環境ということで仕事をしたいと考えていた自分としては、いざ、仕事をやり始めると、プラントの設計だから、ポンプのモーターの設定はどうするかとか配管の材質はステンレスの何番を使うかとか、ガスケットはどうするとか、そんな話ばかりで・・・建築の話とは遠い。やっぱり僕としては、会社には申し訳ないけど、続けていく意味が分からなくなってしまって、7年で清水建設を辞めて、長谷川敬アトリエという個人の設計事務所に移りました。
次世代の民家〜在来の知見に現代の技術を加え、総合的にデザインすること
転職する前から、新しい環境の捉え方を示唆してくれるような本を読むようにしていました。中でも、とても影響を受けたのが『バイオシェルター』という本や、パーマカルチャー関連の本や情報でした。『バイオシェルター』は、アメリカで1970年代くらいから有機農業や再生可能エネルギーなどの研究をしていたニューアルケミー研究所の創始者、ジョン・トッド博士が、約20年間の研究成果をまとめた本です。シェルターという言葉とバイオという言葉が結びつくことを教えてくれて、その頃、僕がいろいろと考えていたことにうまく形を与えてくれた本です。都市の経営とか建築づくりとかまちづくりに生物学を取り入れる発想は、僕としてはとても斬新だったんです。こういう手法があるんだ、と。これこそまさにこれからの都市を作り直す、建築をもう一回ちゃんと定義し直すということの良い切り口になるんじゃないかなと思ったわけです。
そしてさらに『パーマカルチャー 農的暮らしの永久デザイン』という本に衝撃を受けました。パーマネント(永久に)に、アグリカルチャー(農業)、カルチャー(文化)を続けた縮約形の言葉だけど、日本語では「農的暮らし」と記されていました。
農的暮らしと言っても、農業に限定したことではないんです。人間の文明を支えているエネルギーが、枯渇する危機というのもあるわけで、火力も原子力も人類の存亡にデメリットが大きいとなると、やっぱり太陽光エネルギー、太陽熱エネルギーというものに依存するしかないと思います。太陽光エネルギーを地球上で固定化してくれるのは植物だけなんです。そういう意味でも、もちろん作物も含め植物を基盤とした文明を作り直さないといけないのではないか、それ以来ずっとパーマカルチャーの領域を追いかけています。
そういうバックグラウンドで考えてきて、どんな建築に辿り着いたかというと、まず建築は、地域の風土に合った伝統的な工法を下敷きにしなきゃいけないのではないか、ということです。ただ、昔ながらの建築でやっていればいいかというと、そういうわけにもいかない。現代人は、やわになってしまったので、寒さには弱いし、暑さにも弱い。そこは、現代の技術で考えていかないといけない。要は、昔ながらの民家に現代の技術を少し加えながら、次の時代の民家をつくる。その道しかないんじゃないかなと、そういう建築を志向するようになったわけです。

[設計を担当した、坂元植林の家・注文住宅の地鎮祭。後列右から2番目]
.
だから、いわゆる近代建築の、デザインするという行為を、僕としては別の意味で捉えています。多くの人が、デザインって意匠的なかっこいいものつくることだと思っているかもしれません。でも、デザインという言葉の語源から考えてみると、ラテン語のdesignare(デジグナーレ)から来ていて、計画を記号にあらわす、設計するという意味。目に見える形にして方向づけをすることとも言えます。ペンとかノートは単一の機能でいいと思うんだけど、建築みたいに多機能的で多様な状況を実現しなきゃいけないという場や空間だったら、それはある1つの評価軸だけで進めるのは望ましくないと思います。デザインするものが、バランスよくいろいろな機能をちゃんと実現できているかどうか、そんな方向性を示していくことが、住宅、あるいは建築というものに求められるのだと思います。
そう言う意味で、僕は、ただ高断熱のことばかりに終始してしまう家づくりには、少し疑問を持っています。僕は環境系の出身だから、断熱という技術がいかに重要かは重々理解していますが、ただスペックとして、高性能な断熱をトッピングのように施す建築は表層的で、本来良い建築をバランスよく環境的にしていく、というアプローチとは違うと思います。「太陽電池が何キロワット載っています」とか、それだけ足し算で家づくりをして、かつ高断熱を売りにしていても、新建材を多く使った家になっていたり、断熱性能を上げるために窓をどんどん小さくしてしまう例もある。まるで宇宙船のような、カプセルのような家を作っているようなハウスメーカーもあります。寒冷地では特に小さい窓が求められるので。
それから、新建材ではなくて、地元の材や自然素材をできるだけ使って、地元の大工さんと一緒に家づくりをして、地域の経済を回すとか・・・。断熱技術一辺倒ではなく、そういうこともトータルで考えた家づくりが、良い建築と言えるのではないでしょうか。

[2023年3月。建築中のさとのえ。空気層による温熱環境の調節、選択ができるように、外に向けて縁側のような空間を作って建具で仕切り、多層化しています]
環境建築の行く末、第3の道を探る
環境建築の行く末をちょっと心配しています。環境ってもともとトータルなものだし、いろいろな要素が複雑に絡み合っていて、それであるがゆえに安定性というか、秩序があるわけですよね。それが、輪の中で暮らしている僕ら人間の安定性とか安心につながるわけなので。環境をないがしろにして建築を作るということは、やっぱり考えにくいことだと思うのですが。
その場所の気候風土や環境をあまり重視しない建築でもいいという時代もありました。たとえばコルビュジエなどが、ユニバーサルデザインとかインターナショナルスタイルを唱えた時は、全世界同じ建築を作れば、全世界の人はみんな幸せになれるという考え方でした。
折しもそれは1900年代の初頭で、世の中には共産主義的な「みんな平等に幸せを共有できる」という思想が広まっていた時代で、建築もそれに応えるということで、全世界同じ建築で、みんな同じ幸せを共有する・・・、そういう思想だったわけです。
それを可能にしたのが、空調設備です。1800年代の終わり、アメリカのキヤリア社という企業が冷凍技術を開発して、ものを機械的に冷やすことができるようになったんです。それができたことで、超高層のビルとかガラス張りの建築とか、そういうことが可能になった。それと相まって、インターナショナルスタイルみたいな主張が出てきたことから、そういう近代建築が広がりました。
そのときには真面目な動機だったとはいえ、それがやっぱり人間の生命の根源である環境との隔離みたいなことを招いているとしたら、やっぱりそこから、あるべき環境建築のあり方を考え直していく作業が必要なのではないでしょうか。

.
持続可能な社会をつくる市民活動のトランジションタウン運動でもパーマカルチャーでも、「第3の道」というフレーズをよく使います。パーマカルチャーという概念と方法論を提唱したビル・モリソンの第一番弟子でデビッド・ホルムグレンという人がいて、彼は、これからの未来を見通すときに4つのシナリオがあると言っています。その4つを紹介します。
1つ目、はテクノロジーファンタジーと呼ばれていて、人間は優秀だから、これからも技術開発がどんどん進めば環境問題も克服できるし、経済もどんどん発展する。右肩上がりの状態がずっと続くというシナリオです。
2つ目は、環境問題も非常に逼迫している状況の中で、これまでのように右肩上がりではなく、ゆるやかに推移していく、せめて横ばいの状況を保つことで、社会の持続可能性を保つ、という考え方です。その延長で、たとえば高気密・高断熱の住まいづくりで省エネ化が進めばいいということですね。
3つ目のシナリオは、破綻です。気候変動はますます激化して、人類は破滅するしかないという未来です。
4つ目のシナリオが、いわゆるパーマカルチャーとかトランジションタウン運動が志向する世界。これは受け売りの言葉ですけど、「創造的な下降」というものです。これからは、緩やかに下がっていく。資源も有限だし、その使い方をしっかりと持続可能にデザインしながら、創造的に、緩やかに・・・ということです。身の回りにある植物や自然エネルギーをうまく活用して「デザイン」すれば、もっと少ない資源で、もっと少ないエネルギーで暮らせるはずだというのが、パーマカルチャーの基本的な思想です。
上がらない、横ばいでもない、むしろ創造的に下っていく。そういう状況を作るのがパーマカルチャーの目指すところでもあって、だから第3の道ということです。そのあたりに、高気密・高断熱だけではない環境建築のあり方のヒントがあると思っています。(第4回に続く)